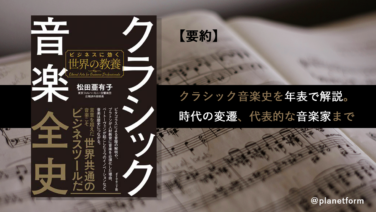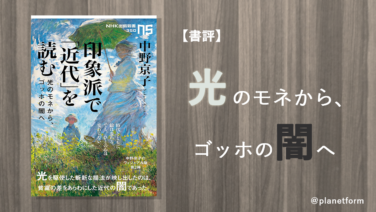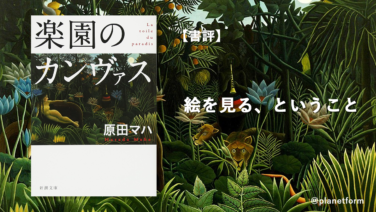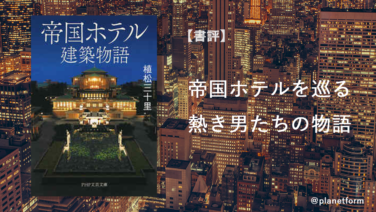 歴史
歴史 【書評】植松三十里『帝国ホテル建築物語』の要約と考察/帝国ホテルを巡る熱き男たちの物語
愛知県の野外博物館・明治村には、多くの明治、大正時代の建物が移設、復元されて公開されています。まるで明治時代にタイムスリップしたかのような感覚を味わいながら、四季折々の自然とどこかからか聞こえてくる汽笛の音を楽しみながら園路を進むと、最初に、石造りの重厚な建物と出会えます。それは帝国ホテル。温かい風合いの黄色いレンガの外壁と、大地にどっしりと構えるその姿、大谷石やテラコッタに彫刻された繊細な幾何学模様はかつて日本を代表したホテルとしての威厳を保ちます。現代の姿は中央玄関とロビー部分だけですが、それだけでも伝わる、このホテルには熱い歴史があります。帝国ホテルの初代支配人である林愛作、設計に関わったアメリカの巨匠フランク・ロイド・ライトと、その弟子であり将来著名な建築家となる遠藤新。帝国ホテルの建設に深く関わった男たちの物語が、本書では語られます。