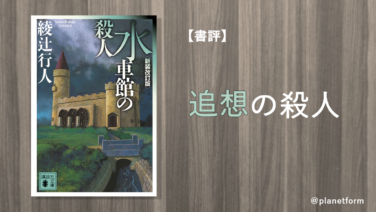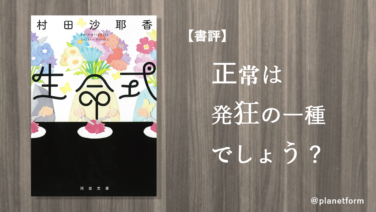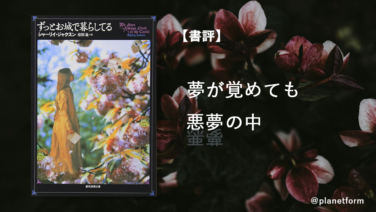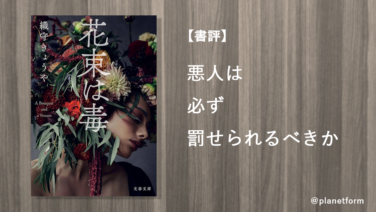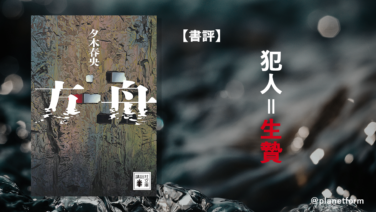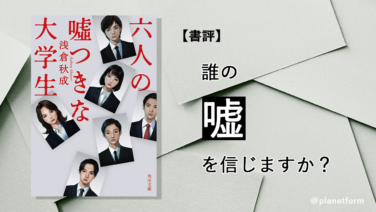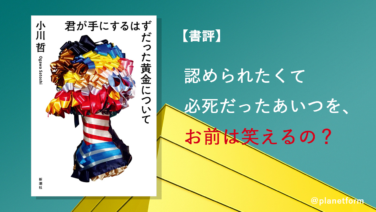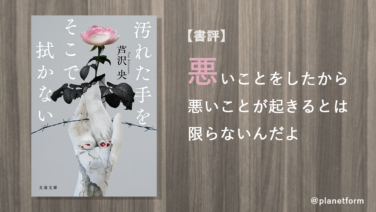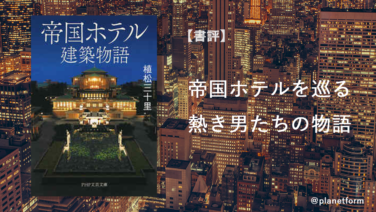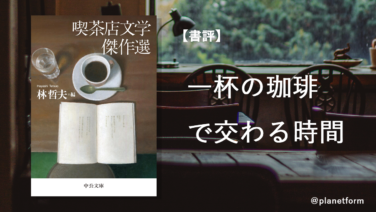 エッセイ
エッセイ 【書評】林哲夫『喫茶店文学傑作選』の要約と考察/一杯の珈琲で交わる時間
本書『喫茶店文学傑作選』は、明治から平成に至るまでの作家28名による喫茶店を舞台に書かれたエッセイや小説を纏めたアンソロジーです。喫茶店という場の時代の変遷を感じられるだけでなく、喫茶店で一杯の珈琲を頂く、ひと時の時間を豊かにしてくれる美しい作品集です。喫茶店という場喫茶店とは、様々なバックグラウンドを持つ人々が集い、それぞれの時間を交錯させる非常に稀有な場所です。人々が交錯した時、そこに物語は生まれます。同じく喫茶店にて時間を過ごした作家たちは、その物語性に惹きつけられ、本書に記されたような物語を書き残しました。そんな物語を読んでいると、まるで自らもその時代にタイムスリップし、ひと時の時間を共に共有しているような感覚にさせられます。珈琲一杯分というその濃密な味わい深い時間を、共に共有してみませんか。