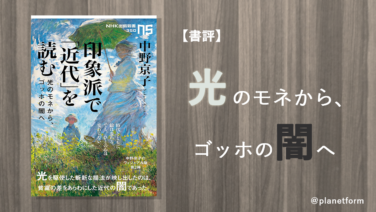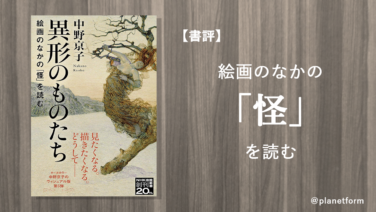 芸術
芸術 【書評】中野京子『異形のものたち』の要約と考察/絵画のなかの「怪」を読む
本書『異形のものたち』では、尋常ならざる形態に魅入られた画家たちによる欲求を、美麗な絵画の解説とともに紹介してくれます。この世にないものに対する「見たい」という好奇心、曰く言い難い気配や雰囲気の絵画的創出、本書は、そんな「怪」を、人獣、蛇、悪魔と天使、キメラ、ただならぬ気配、妖精・魔女、魑魅魍魎のキーワードをもとに語っています。しかし、「異形」を画題にした絵画と聞くとどこか物珍しく感じるかと思いますが、古来から伝わる神話や宗教では、当然のように「異形」は登場します。そう考えると、「異形」とはそもそも物珍しいものなどではなく、人間心理の根底では情念の対象なのでしょう。古今東西異形フェチには本書を是非おすすめします。