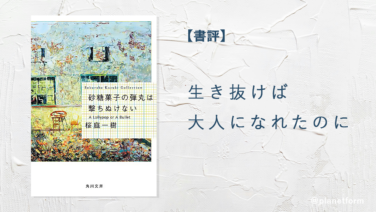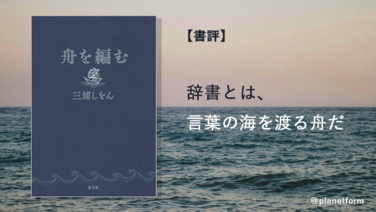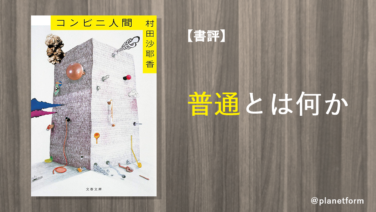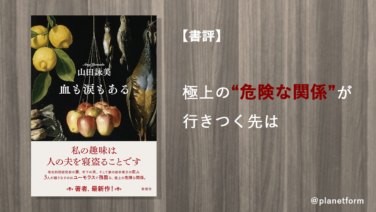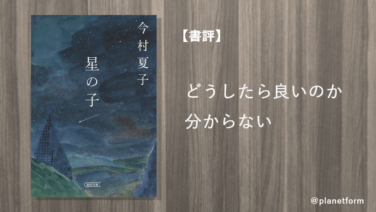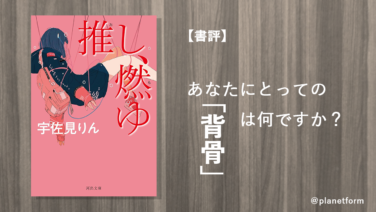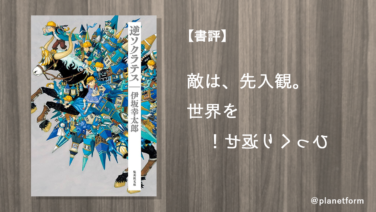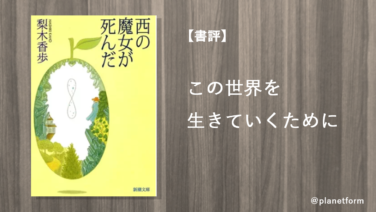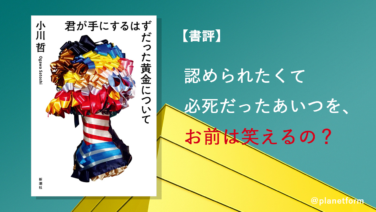 日常
日常 【書評】小川哲『君が手にするはずだった黄金について』の要約と考察/認められたくて必死だったあいつを、お前は笑えるの?
『君が手にするはずだった黄金について』は、自らを振り返る機会を与えてくれる小説です。物語の主人公「僕」は作家・小川哲。本作の著者と同じ名前を持つ「僕」は、作中を生きる中で様々な人々と出会い、人々の分析を通して、自身の思考や行動に自問自答します。つまり、本書は作者である小川哲自身のエッセイなのかと最初は思いますが、どうやらそうではないらしい。しかし、作中で起きた一部の出来事や、それに対する「僕」の思考自体は、もしかしたら事実として経験した事なのかもしれないと、思わせもします。読者は、この現実と創作が入り混じる物語を読んで、自らも作中の登場人物または主人公と共鳴し、自分自身のことについても疑問を覚えるようになります。もし自分ならどう考えるか、どんな行動をするか。自分とは何者なのか、存在価値や価値観までもがぐらりと揺らぐような感覚になります。じっくりと考えさせられてしまう小説でした。「あなたの人生を円グラフで表現してください」プロローグで問われたこの問いが、最後まで心に残ってます。